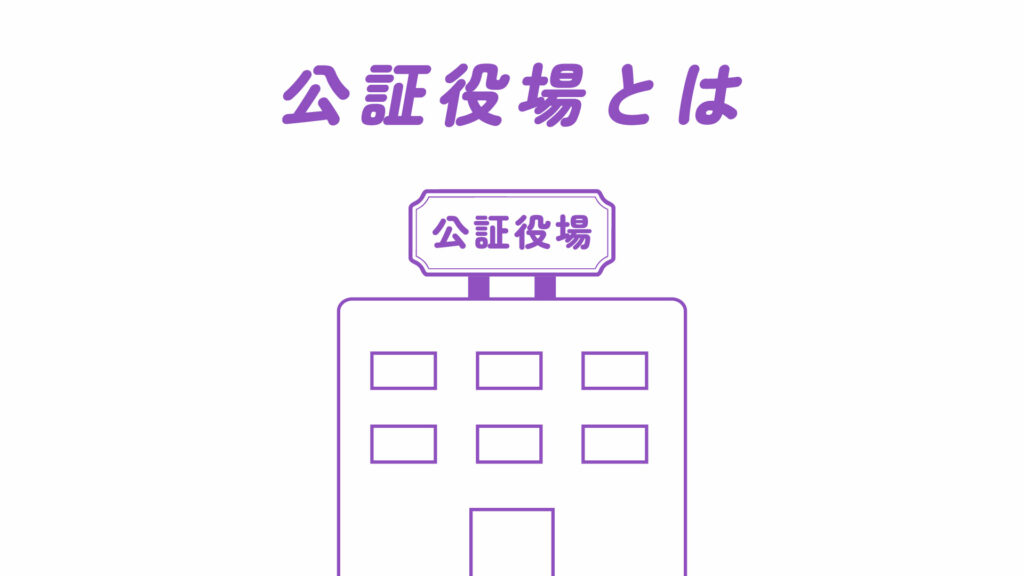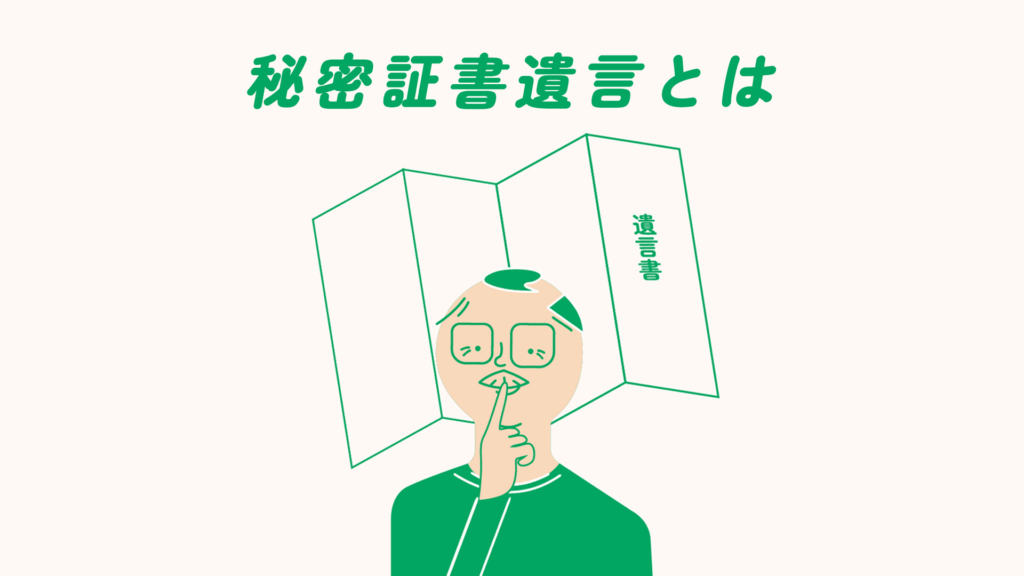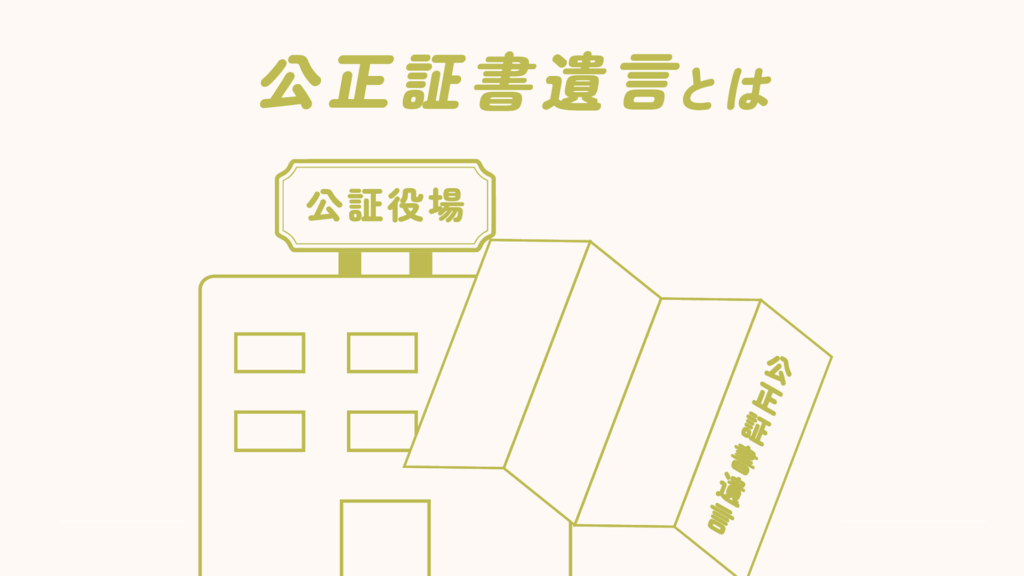相続が発生すると、遺産分割や名義変更、税金の申告など、多くの手続きを行う必要があります。しかし、手続きの中には専門的な知識が求められるものや、期限が定められているものもあり、すべてを自分で対応するのは難しい場合があります。
そのようなときに頼れるのが、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家です。しかし、「どの手続きを誰に相談すればいいのか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続手続きの種類ごとに、各士業が対応できる業務内容をわかりやすく整理し、自分に最適な専門家を選ぶポイントを解説します。相続手続きで困ったときに、スムーズに解決できるよう、ぜひ参考にしてください。
相続手続きは誰に相談すべき?
相続が発生すると、ただでさえ故人を失った精神的な負担がある中で、膨大な手続きを進めなければなりません。
「何から始めればいいのかわからない…」
「平日は仕事があるのに、役所や金融機関の手続きを進められるのか?」
「手続きを間違えたら、取り返しのつかないことになるのでは?」
このような不安を抱えながら、すべての手続きを自分で行うのは想像以上に大変です。
相続手続きの主な流れと必要な作業
① 戸籍の収集(相続関係を証明するため、数十年分の戸籍を遡る必要あり)
「戸籍の取得なんて簡単でしょ?」と思うかもしれませんが、実はかなり手間がかかります。
相続人を確定するためには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。
手続きの流れ
- 最寄りの役所に故人の戸籍謄本を請求
- 相続人全員の戸籍謄本を取得(兄弟や甥姪が相続人となる場合、関係を証明する戸籍も必要)
ここが大変!
- 役所は平日しか開いていないため、仕事をしながら手続きを進めるのは難しい
- 直系親族の戸籍謄本は最寄りの役所で取得が可能である一方で、傍系親族(兄弟姉妹)はその本籍地の役所に請求する必要があり、本籍地が遠方の場合、郵送請求が必要になり、やりとりに時間がかかる
- 戸籍制度の変遷により、古い戸籍の解読が難しく、専門知識が求められる
② 財産の調査(不動産・預貯金・株式など、すべての財産を把握する)
相続財産がどこにどれだけあるのかを正確に把握する必要があります。
故人が所有していた不動産、預貯金、株式、生命保険などを洗い出し、場合によっては財産目録を作成しなければなりません。
手続きの流れ
- 故人の通帳や証券会社の書類を調べ、金融機関や証券会社に照会
- 不動産の登記簿謄本を法務局で取得し、所有状況を確認
- 借金や未払いの税金がないかも調査(負債の相続放棄の判断材料になる)
ここが大変!
- 故人が複数の銀行や証券会社と取引していた場合、1つ1つ照会する必要がある
- 銀行や証券会社ごとに対応が異なり、必要書類が複雑
- 借金や未払い税金がある場合、相続放棄の期限(3ヶ月以内)に間に合うように判断しなければならない
③ 遺産分割協議書の作成(法的に有効な形式で作成し、全員の実印と印鑑証明が必要)
遺産分割協議書は、相続人全員が納得できる形で財産を分けるための重要な書類です。この書類がなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約ができないケースがほとんどです。
手続きの流れ
- 相続人全員で話し合い、誰がどの財産を受け取るのか決める
- 法的に有効な遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印
- 各相続人の印鑑証明書を取得し、書類に添付
ここが大変!
- 相続人が複数いる場合、意見がまとまらず協議が長引く可能性がある
- 法的に不備のある書類を作成してしまうと、金融機関や法務局で受理されない
- 印鑑証明書の取得や書類のやりとりが煩雑
④ 不動産・預貯金・有価証券の名義変更(金融機関ごとに異なる手続きを確認)
故人名義の財産を相続人の名義に変更するために、それぞれの機関で手続きを行います。
手続きの流れ(例:銀行口座の名義変更)
- 銀行の窓口やウェブサイトで相続手続きを申請
- 必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の署名など)を提出
- 書類審査後、名義変更や口座解約が完了
ここが大変!
- 銀行によって必要書類が異なり、何度もやりとりが発生することも多い
- 相続人が多い場合、全員の同意を求められるとスムーズに進まないことがある
- 有価証券(株式・投資信託)や海外資産の相続は、さらに手続きが複雑になる
⑤ 相続税の申告(税務署への書類提出、期限内の納税)
遺産総額が基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。
手続きの流れ
- 相続財産を評価し、相続税額を計算
- 各相続人の納税額を決定し、申告書を作成
- 相続税を相続開始から10ヶ月以内に納税
ここが大変!
- 相続税の計算が非常に複雑で、専門的な知識が求められる
- 期限を過ぎると延滞税が発生するため、遅れると大きな負担になる
- 申告書類が膨大で、税務署の審査が厳しい
相続手続きは、単に役所や金融機関に書類を提出するだけではなく、膨大な作業と専門知識が求められるため、スムーズに進めるのが難しいケースも少なくありません。
また、手続きには期限があるものも多く、後回しにすると思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
そのため、自分の状況に合わせて、専門家のサポートを検討することも一つの選択肢です。
特に、書類作成や名義変更などの手続きに不安がある場合は、行政書士や司法書士に相談することで、手続きがスムーズに進むこともあります。
まずは、どの手続きが必要なのかを整理し、自分で対応できることと専門家に相談したほうがよいことを見極めることが大切です。
各士業が対応できる相続に関する手続き一覧表
| 手続き | 期限 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
| 法定相続人調査 | なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 相続財産調査 | なし | △※1 | △※1 | △※1 | ○ |
| 相続放棄申立 | 3ヶ月以内 | ○ | ○ | × | × |
| 遺言検認の申立 | 遺言発見後すみやかに | ○ | ○ | × | × |
| 遺産分割協議のサポート | なし | ○ | × | × | × |
| 遺産分割協議書の作成 | なし | △※2 | ○ | ○ | × |
| 相続人間の紛争解決 | なし | ○ | × | × | × |
| 遺留分侵害請求 | 1年以内 | ○ | × | × | × |
| 相続税の申告 | 10ヶ月以内 | × | × | × | ○ |
| 準確定申告の代行 | 4ヶ月以内 | × | × | × | ○ |
| 節税対策のアドバイス | なし | × | × | × | ○ |
| 相続税の還付請求 | 5年以内※5 | × | × | × | ○ |
| 不動産の名義変更 | なし | × | ○ | × | × |
| 預貯金の解約払い戻し | なし | △※3 | △※3 | △※3 | × |
| 有価証券の名義変更 | なし | △※3 | △※3 | △※3 | × |
| 自動車の名義変更 | なし | △※3 | △※3 | ○ | × |
| 死亡一時金の受け取り請求 | 2年以内 | △※4 | × | △※4 | × |
| 死亡届・火葬許可申請書 | 7日以内 | × | × | ○ | × |
| 年金受給停止・健康保険資格や世帯主の名義変更 | 14日以内 | × | × | ○ | × |
※1 相続財産調査:調査範囲によって対応する専門家が異なります。弁護士は裁判手続きが必要な場合やトラブルが発生している場合に対応します。司法書士・行政書士は書類作成や役所調査の範囲で対応可能です。
※2 遺産分割協議書の作成:司法書士・行政書士が作成できますが、相続人間で争いがある場合は弁護士が介入し、法的な交渉を行う必要があります。
※3 預貯金・有価証券・自動車の名義変更:手続き内容により各専門家が対応します。特に、争いがある場合や法的な代理が必要な場合は弁護士、登記が関係する場合は司法書士が担当します。
※4 死亡一時金の受け取り請求:ケースによっては弁護士がサポートできるが、基本的には遺族自身が対応することが多いです。
※5 相続税の還付請求:相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)から5年以内とされています。したがって、相続開始から起算すると5年10ヶ月以内となります。
最後に
相続手続きには、法的な知識や税務の知識が必要なものが多く、専門家のサポートを受けることで手続きをスムーズに進めることができます。
- 弁護士 → 相続人間のトラブルや法的交渉が必要な場合
- 司法書士 → 不動産登記や相続関係書類の作成が必要な場合
- 行政書士 → 各種書類作成や名義変更の手続きをスムーズにしたい場合
- 税理士 → 相続税の申告や節税対策が必要な場合
また、相続には期限がある手続きも多いため、放置してしまうと後から大きなトラブルになることもあります。早めに専門家へ相談し、「自分でできること」と「専門家に任せるべきこと」を明確にしておくことが重要です。
相続に関する不安や疑問を解消するためにも、まずは信頼できる専門家に相談し、適切な対応を進めていきましょう。